
心電図ってよくわかんない。
っていうか放射線技師って心電図撮らないし知らなくていいんじゃない?
そんなことを考えていた3年前の自分へ。シャラーーーーーップ!!
胸部レントゲンとか腰椎レントゲンとかひたすら撮るだけなら心電図の地域なんて一切要りません。使うことないからね。
でも心臓CTを撮るとなると心電図は避けて通れない道です。心電図の難しい話は専門書にお任せして、ここでは知っておけば心臓CTが捗る知識だけに厳選して教えます。

この記事を読めば最低限の心電図知識が身につく!
①正常波形というものを把握する

心臓は電気刺激で心筋が収縮して血液を送るポンプを担っています。心電図波形はその電気刺激を表したもので、心臓がギュッと収集するたびに、この波形は1つ現れます。
波形は大きくP波・QRS波・T波に分かれます。
P波
P波は心電図波形の最初に出てくる小さな波で、心房の興奮をあらわしています。

そのため、P波がおかしい=心房側異常による不整脈 ということになります。
QRS波
QRS波はP波の後に出てくる大きな波で、心室の興奮をあらわしています。

そのため、QRS波がおかしい=心房側異常による不整脈 ということになります。
なんでP波よりQRS波の方が大きいの?

それは心室の方が分厚くて、収縮させるのに大きなエネルギーが必要だからだよ!
T波
QRS波の後に出てくる中くらいの波で、心室興奮が冷めるときに出てきます。
不整脈解析には向かない波形なのでスルーしてOKです。
②心臓CTで大事なことは止まった瞬間を撮ること
正常波形の簡単な意味がわかりましたね。次は実際の検査で役立つ情報です。
当たりまえですが、心臓は生きている限り動き続けていて止まることはありません。しかし冠動脈を撮るにあたってなるべく止まった瞬間を撮影したいのが心臓CTです。
心臓は収縮と拡張を繰り返していますが、ちょこっとだけ止まる瞬間があるのです。それが収縮末期と拡張中期です。ようは心臓が一番ちっちゃくなったときと、大きく膨らんだすぐのタイミングです。

上の図が正常波形、下のグラフが左室の容積をあらわしています。
収縮末期
心房が興奮し(P波)、続いて心室が興奮(QRS波)すると心臓がググッと収縮します。もっとも収縮したタイミングを収縮末期といいます。
拡張中期
収縮がおわると心臓は膨らんでいきます。膨らんだ後に容積が安定するタイミングがあります。それが拡張中期です。
心拍数が60程度とゆっくりなら収縮末期より拡張中期の位相をつかって撮影するのがベストです。
逆に心拍数は早いと拡張中期が短くなってしまうため、収縮末期のタイミングを狙うのがベストです。

心拍数が早くなると収縮時間は変わらないけど、
拡張時間は短くなってしまうよ!
まとめ
今日は心臓CTで必要な超最低限な情報をお伝えしました。
心臓CTは拡張中期を狙え!もしくは収縮末期を狙え!これは常識です。
これを知っておけば撮影後に最適位相をチョイスするときにだいたいの静止位相がわかるので便利ですね♪

ではでは、また明日~♪



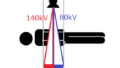
コメント